ホームページ移転のお知らせ
「わいず倶楽部」ホームページは移転しましたので、今後は下記ドメインからアクセスをお願いいたします。
【変更後URL】
https://ysclub.yomiuri.co.jp/
※10秒後に新ホームページのトップページへ自動転送されます。
TEL:06-6366-2338
(10:00~17:00、土日・祝を除く)
Copyright © The Yomiuri Shimbun. All rights reserved.
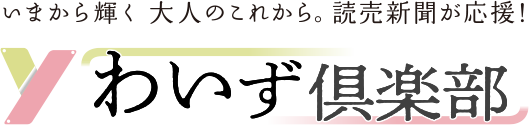
「わいず倶楽部」ホームページは移転しましたので、今後は下記ドメインからアクセスをお願いいたします。
【変更後URL】
https://ysclub.yomiuri.co.jp/
※10秒後に新ホームページのトップページへ自動転送されます。